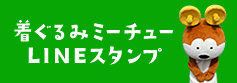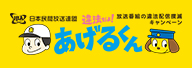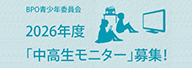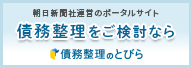vol.179 大腸がん検診について
2013年10月27日
食生活の欧米化などにより増加傾向にある大腸がん。現在は男女合わせて胃がんに次いで二番目に多い罹患数になっている。詳しいお話を県医師会の及川圭介先生に伺った。
大腸は奥から盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸と名前がついている。大腸がんの約7割は、S状結腸と直腸に発生する。大腸がんは正常な粘膜の何もないところから発生することがあるが、多くは腺腫というポリープから発生する。したがってポリープは前がん病変といえる。
大腸がんは進行して腫瘍が大きくなると血便や腹痛などの症状が出てくるが、早期の大腸がんや前がん病変であるポリープはほとんど症状がない。そのため早期発見には検診を受けることがとても重要だ。大腸がん検診は簡単な検便検査で行う。極微量の血液の混入を調べる便潜血免疫反応を調べる。食事制限もなく手軽にできるのでぜひ受けてほしい。
大腸がん検診の対象年齢は40歳以上だが、歳を重ねるにつれて増えてくるので、毎年受けることが重要だ。大腸がん検診は大腸がんを発見するきっかけになる。早期のうちに発見できれば100%近く治せるし、極早期のものであれば内視鏡で治療することも可能だ。ぜひ検診を受けてほしい。